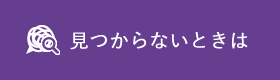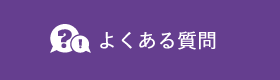北国街道と野々市
北国街道と野々市
江戸時代の北国街道は、五街道(ごかいどう)[江戸を出発地とする東海道(とうかいどう)、中山道(なかせんどう)、日光(にっこう)街道、奥州(おうしゅう)街道、甲州(こうしゅう)街道]に次いで重要な街道でした。
加賀藩では、野々市を金沢城下から京都へ向かうときの最初の宿駅(しゅくえき)として整え、荷物を運ぶための人や馬をいつも準備させていました。備えておく馬の数が決められていて、1666年[寛文6]の野々市は87疋(ひき)で、津幡118疋、鶴来115疋、宮腰[金沢市金石]96疋についで4番目の多さでした。
駅馬(えきま)による輸送は、次の宿駅に着いたら、そこに備えてある馬に荷物を載せかえて次の宿駅に運ぶ方法がとられました。荷物を隣りの宿駅に運んだ駅馬は、今度は別の荷物を載せて元の宿駅に戻ってくることになります。
野々市は、金沢城下から最初の宿駅であったことから、京都方面へ向かう旅人を野々市まで同行して見送りしたり、野々市で着物を着替えて金沢城下に入った、という話も伝わっています。

本町2丁目にたてられている石碑(せきひ)

北国街道だった本町通り
市内には、押野から本町・稲荷・三日市・徳用・郷にかけて旧北国街道の道筋を確認することができます。