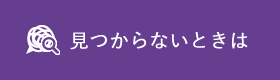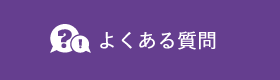雑損控除の申告について
1.概要
自然災害や火事等の災害、盗難等によって、個人が所有する生活用資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合には、以下で説明する手順によって計算した金額を「雑損控除」として、損害を受けた年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。
2.対象となる災害等
雑損控除が適用される災害等は、次のとおりです。なお、詐欺や恐喝が原因である損害には、適用されません。
- 震災、風水害、冷害、干害、落雷など、自然現象の異変による災害
- 火災、鉱害など、人為による異常な災害
- 害虫など、生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
3.対象となる資産
雑損控除の対象となる「生活用資産」とは、「生活に通常必要な資産」をいいます。事業用資産や生活に通常必要でない資産等は対象となりません。また、その資産の所有者は、次のいずれかである必要があります。
- 納税者本人
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者
4.控除額の計算
控除額は次のアとイうち、いずれか多い方の金額です。
ア 損失額(保険金等で補填される金額を除く) - 総所得金額等の1/10
イ 損失額のうち災害関連支出の金額(保険金等で補填される金額を除く) - 5万円
(注1)「損失額」とは、「住宅家財等の損失の金額」と「災害関連支出の金額」を合計した額です。
(注2)「住宅家財等の損失の金額」とは、被害が発生した直前の時価と、被害が発生した直後の時価との差額となります。なお、被害を受けた住宅家財等を廃棄し、新たに購入した場合の購入金額は算入されません。
(注3)「災害関連支出の金額」とは、被害を受けた住宅や家財等の取壊し、除去、現状回復費用など、災害等に関連したやむを得ない費用をいいます。
5.手続き
雑損控除の適用を受けるには、次に掲げる書類をご用意のうえ「雑損失の金額の計算書<外部リンク>」を作成し、個人市・県民税の申告書とあわせて提出してください。なお、必要に応じて関係書類の提出をお願いする場合があります。なお、所得税の確定申告で「雑損控除」を申告した場合は、市・県民税申告書の提出は不要です。
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価格が分かるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの
- 損害に対し、保険金等で補てんされる金額が分かるもの
- (災害の場合)「罹災証明書」の写し(又は被害が確認できる写真等)
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています)。
被害を受けた資産の損失額を計算することが困難な場合
被害を受けた資産の取得価額が不明な場合や、被害が大きく住宅家財の損壊の程度を個別に把握することが困難な場合等は、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書 [PDFファイル/327KB]」により計算した金額を損失額として申告してください。書き方等、不明な点がありましたら管轄の税務署にお問い合わせください。
6.災害減免法による軽減免除の申告について
所得税の確定申告では、雑損控除との選択により、災害減免法に定められた軽減免除の適用を受けることができます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際にご自身で選択できます。
ただし、軽減免除の適用を受けた場合には、その内容は住民税には反映されませんので、雑損控除を含めた市・県民税の申告を別に行う必要があります。
災害減免法による軽減免除については、お住まいの区を所管する税務署へご相談ください。
7.関連情報
雑損控除の適用等については、こちらもご覧ください。
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)【国税庁】<外部リンク>
No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除【国税庁】<外部リンク>