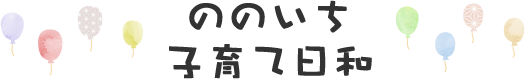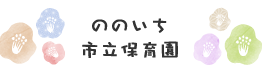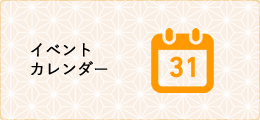子育て支援医療費助成
助成対象
0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども
助成額
入院や通院などにかかる医療費(健康保険適用分)を全額助成します。
※健康保険適用の歯科治療や院外処方箋による薬代、整骨・接骨・鍼灸院等の療養費、他の公費負担医療制度(育成医療・小児慢性特定疾病医療費など)に係るものも対象です。
助成対象にならないもの、金額を差引するもの
・健康保険が適用されない場合(薬の容器代、予防接種、文書料、入院時の食事療養費、差額ベッド代など)
※予防接種は「子ども予防接種費用助成」があります。こちらの申請は保健センター(健康推進課)まで:076-248-3511
・健康保険から高額療養費や付加給付が支払われる場合は、その金額を差し引きます。
助成方法1 現物給付
医療機関で受給資格証を提示すると、窓口負担が無料になります。
受給資格証交付の手続き
助成対象となる子どもが出生または転入した場合等は、下記の書類を提出してください。受給資格認定後、「野々市市子育て支援医療費受給資格証」(以下「受給資格証」と表記します。)を郵送します。(※申請受付日から約2週間かかります。)
【必要書類】
- 子育て支援医療費助成金受給資格認定申請書 [PDFファイル/127KB]
- 申請者(保護者)の本人確認書類
- 子どもの保険情報の分かるもの(出生による申請の場合は、子どもが今後加入する予定の保護者の保険情報の分かるものでも可)
- 保護者名義の振込口座の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど ※子ども名義不可)
【下記に該当する場合は、医療機関の窓口で受給資格証を提示しないください】
- 交通事故など、第三者行為による診療の場合
- 学校や保育園等の負傷など、日本スポーツ振興センターの給付金対象となる場合
助成方法2 償還払い
下記に該当する場合、窓口負担が無料にならないので助成金の申請が必要です。
- 受給資格証を提示しないで受診した場合
- 県外の医療機関で受診した場合
- 受診する医療機関が受給資格証に対応していない場合
- 治療用補装具を作った場合
償還払いの助成金申請手続き
医療機関を受診した際に受給資格証が利用できず、保険診療の2割または3割などの自己負担額を支払った場合、下記の通り申請してください。
【必要書類】
- 医療費助成申請書 [PDFファイル/125KB]
- 領収書(原本)※氏名・診療年月日・保険点数・本人負担額・保険分保険外の記載・領収印のあるもの
- 申請者(保護者)の本人確認書類
- 保険情報の分かるもの
- 受給資格証
【申請期間・振込】
- 診療月の翌月の初日から1年以内に申請してください。(例:4月診療分は5月から翌年の4月まで申請できます)※転出する場合のみ当月診療分の申請ができます。
- 申請月の翌月の月末に指定の口座へ助成金を振り込みます(例:4月申請↠5月末振込)
健康保険組合への申請が必要となる場合
下記に該当する場合は、事前に加入している健康保険組合に申請が必要です。申請後、支給額を確認できる書類(療養費支給決定通知書など)を持ってくるのうえ子育て支援課に申請してください。
| 治療用眼鏡 や補装具を作った場合 |
高額療養費や付加給付が支給される場合 |
保険証を持ってくるせず医療費全額(10割)を支払った場合 |
|---|---|---|
|
・眼鏡、補装具購入時の領収書 ・指示書または診断書など ・療養費支給決定通知書 |
・領収書 ・療養費支給決定通知書 |
・領収書 ・療養費支給決定通知書 |
※領収書及び指示書・診断書などはコピーの提出でも可能です。
※健康保険組合が発行する療養費支給決定通知書は必ず原本を提出してください。
その他の手続き
住所・氏名・加入保険・振込口座の変更がある場合
住所・氏名・加入保険(記号・番号のみが変わった場合も含む)・振込口座が変更となる場合は、下記の書類を持ってくるのうえ届出してください。
【必要書類】
- 子育て支援医療費助成金受給資格変更届 [PDFファイル/92KB]
- 届出者(保護者)の本人確認書類
- 受給資格証(※住所・氏名変更の場合)
- 子どもの保険情報の分かるもの(※加入保険変更の場合)
- 口座のわかるもの(※振込口座変更の場合)
受給資格証を紛失した場合
受給資格証を紛失・破損した場合は、下記の書類を持ってくるのうえ申請してください。また、電子申請フォームより申請していただくことも可能です。
【必要書類】
- 子育て支援医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/58KB]
- 申請者(保護者)の本人確認書類
【電子申請はこちらから】
https://logoform.jp/f/Auqio<外部リンク><外部リンク>

事前準備をしていただくもの
1 マイナンバーカード
2 マイナンバーカードの暗証番号(4桁の暗証番号と6~16桁の暗証番号)
3 スマートフォンに「電子認証 マイナサイン」アプリのインストール
「電子認証 マイナサイン」アプリのインストール
Androidをご利用の方
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cyberlinks.mynasign<外部リンク><外部リンク>
Iphoneをご利用の方
https://apps.apple.com/jp/app/電子認証-マイナサイン/id1645266445<外部リンク><外部リンク>
受給資格証の返却が必要な場合
市外へ転出した場合や生活保護法の適用を受ける場合は、受給資格証を返却してください。