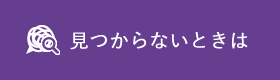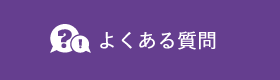特別障害者手当
身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給されます。
対象となる方
20歳以上の障害のある方で、障害程度が次の認定基準に該当する方が特別障害者手当の支給対象となります。
※診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方でも特別障害者手当に該当する場合もあります。審査の結果、認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。
- A表から2項目以上に該当する方
- A表から1項目とB表から2項目以上に該当する方(ただし、A表とB表で同一の障害はカウントできません)
- A表の3~5のいずれかの項目に該当し、かつ日常生活動作評価表の項目が10点以上の方
- 障害児福祉手当における日常生活の自立ができない程度の障害または病状(内部障害など)に該当し、日常生活上絶対安静の状態にある方
- 障害児福祉手当における精神の障害に該当し、日常生活能力判定表の合計点数が14点以上となる方
|
|
| 動作 | 評価 |
|---|---|
|
ひとりでできる場合 0点 ひとりでできてもうまくできない場合 1点 ひとりでは全くできない場合 2点 |
| 注(1) 2の場合については次によること 5秒以内にできる 0点 10秒以内にできる 1点 10秒ではできない 2点 注(2) 3及び4の場合については,次によること 30秒以内にできる 0点 1分以内にできる 1点 1分ではできない 2点 |
| 動作及び行動の種類 | 0点 | 1点 | 2点 |
|---|---|---|---|
| 食事 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
| 用便(月経)の始末 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
| 衣服の着脱 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
| 簡単な買物 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
| 家族との会話 | 通じる | 少しは通じる | 通じない |
| 家族以外の者との会話 | 通じる | 少しは通じる | 通じない |
| 刃物・火の危険 | わかる | 少しはわかる | わからない |
| 戸外での危険から身を守る(交通事故) | 守ることができる | 不十分ながら守ることができる | 守ることができない |
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について [PDFファイル/582KB]
対象外となる方
障害程度が上記の認定基準に該当する方でも、次の項目に該当する方については、特別障害者手当の支給はされません。
- 日本国内に住所を有しなくなった方
- 病院、診療所、介護医療院、介護老人保健施設に継続して3カ月以上入院している方
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得限度額を超える方(所得限度額については、特別障害者手当について(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。)
- 以下の支給対象外施設に入所している方(通所している場合を除く)
|
施設の種類 |
|---|
| 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム |
| 障害者支援施設(生活介護に限る) |
| 障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院または障害者支援施設 |
| 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 |
| 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等の進行性筋萎縮症者の治療等を行う施設 |
| 国立保養所 |
| 生活保護法に規定する救護施設または更生施設 |
(参考)以下の施設に入所している場合は、特別障害者手当の支給対象となります。
|
施設の種類 |
|---|
| 宿泊型自立訓練施設 |
| 共同生活援助(グループホーム) |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 |
|
特定施設入居者生活介護施設(地域密着型含む) |
| サービス付き高齢者住宅 |
|
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
| 自動車事故対策機構療護センター |
| 女性自立支援施設(婦人保護施設) |
※自分の施設が対象になるか不明な場合は、福祉総務課までお問い合わせください。
特別障害者手当における施設入所の取り扱い [PDFファイル/61KB]
支給額
月額 29,590円
支給日
特別障害者手当の支給日は、毎年、2月・5月・8月・11月の10日です。
申請時に指定された障害者本人の口座に支給します。
※振込日が金融機関休業日のときは、直前の営業日になります。
| 支払日 | 支払月分 |
|---|---|
| 2月10日 | 11~1月分 |
| 5月10日 | 2~4月分 |
| 8月10日 | 5~7月分 |
| 11月10日 | 8~10月分 |
申請方法
福祉総務課窓口(1階6番)で認定請求をする必要があります。必要書類や手続きについてご案内しますので、事前に福祉総務課窓口でご相談ください。
必要書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 医師の診断書(障害の種類によって診断書の様式が異なります。)
- 特別障害者手当所得状況届
- 障害者本人名義の預金通帳やキャッシュカードなど振込先口座が確認できる書類
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど個人番号が確認できる書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 非課税の年金(障害年金・遺族年金等)の振込通知書(受給している方のみ)
※原則、診断書の内容により可否の決定を行います。認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。また、診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
※該当する要件や状況によって、必要書類が異なる場合もあります。申請前に必ず福祉総務課でご相談ください。
その他の届出
所得状況届
毎年8月12日から9月11までに所得状況届を提出する必要があります。対象者には案内文を送付しますので、期間中に提出してください。
氏名・住所・口座が変わったとき
氏名が変わったときや、住所が変わったときは、氏名・住所変更届を提出する必要があります。
振込先口座が変更になった場合は、振込先口座変更申出書を提出する必要があります。新しい振込先口座が分かる通帳やキャッシュカードなどをお持ちください。