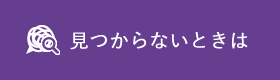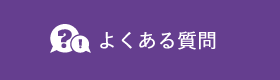国民年金
国民年金
国民年金はすべての国民の老後の生活保障だけでなく、重い障害や死亡といった万が一のときに、生活の安定が損なわれることのないよう、みんなで前もって保険料を出し合うことで相互扶助を行う制度です。日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入することとなっています。
国民年金の加入者
| 1.第1号被保険者 | 日本に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人など (2・3以外の人) |
|---|---|
| 2.第2号被保険者 | 会社員、公務員など |
| 3.第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者の保険料は、月額17,510円(令和7年度)です。
保険料の納付期限は、翌月末(例えば4月分は5月末まで)です。
また、保険料をまとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。
定額保険料に加えて、1カ月あたり400円の付加保険料を納付すると、納付月数に応じて受け取る年金額の年額が「200円×納付月数分」上乗せされます。付加保険料の納付には申し込みが必要です。
保険料の納め方
納付書「領収(納付受託)済通知書」
日本年金機構から送付されます。
納付書裏面に記載のある金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めてください。また、電子納付(Pay-easy)やスマートフォン決済アプリでも納付できます。
紛失した場合は、年金事務所に問い合わせてください。
口座振替
口座振替で納めると手間がなく、納め忘れを防ぐことができます。
申し込み手続きは、年金事務所または金融機関窓口で受付しています。
クレジットカード納付
クレジットカードで納めると手間がなく、納め忘れを防ぐことができます。
申し込み手続きは、年金事務所で受付しています。
保険料の免除・納付猶予
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」されます。
学生の人は学生納付特例を利用してください。
このほか、国民年金保険料第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度(産前産後期間の免除制度)があります。
これから受給する人(60歳から65歳)
年金は請求しなければ受給できません。65歳から老齢基礎年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する人には、65歳になる3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。
国民年金に関する届出
| こんなとき | 手続きできる人 | 必要な書類 |
|---|---|---|
|
会社を退職したとき |
|
|
|
厚生年金(旧共済組合)の加入者の配偶者で扶養から外れたとき |
|
|
|
付加保険料の納付を希望するとき |
|
|
| 産前産後期間の免除を申請するとき |
|
|
|
|
|
|
国民年金受給者が死亡したとき |
状況に応じて変わりますので、問い合わせてください。 |
|
|
任意加入(脱退)するとき |
|
|
※「手続きできる人」以外の人が手続きするときは、委任状が必要です。様式は問いません。