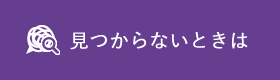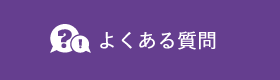戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号。以下「特弔法」といいます。)に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法(大正12年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)(以下「援護法」といいます。)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族(以下「年金給付の受給権者」といいます。)がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)
特別弔慰金の支給
特別弔慰金は、戦後何十年といった機会をとらえて支給されるほか、この節目と節目の間に年金給付の受給権者が死亡したこと等により、基準日に年金給付の受給権者がいない場合には特例的な特別弔慰金が支給されています。
戦後80年に当たる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を年5万5千円に増額することになりました。支給は、記名国債により行われ、その名称、額面及び償還期間は以下のとおりです。
令和7年改正の特別弔慰金
令和7年の特弔法の改正においては、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することから、新たな基準日を令和7年4月1日及び令和12年4月1日と定めています。ここでは、令和7年4月1日を基準日とする第十二回特別弔慰金について説明します。なお、令和12年4月1日を基準日とする特別弔慰金(5年後)については、令和12年4月1日から請求受付を開始する予定であり、改めて請求手続をしていただくことになります。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金を支給します。
国債の名称・額面
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅してしまうので、ご注意ください。
請求書の受付機関
野々市市役所 福祉総務課
※請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する市区町村です。なお、請求者が外国に居住している場合は、請求手続、国債の受領及び償還金の受領を委任された代理人の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。また、法定代理人または相続人による請求の場合は、これらの者の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。
基本的な支給要件
特別弔慰金の基本的な支給要件は次のとおりです。
| 内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料等の年金給付の受給権者がいないこと | 基準日である令和7年4月1日において、戦没者等の死亡に関し年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族)がいないことです。実際に年金給付の裁定を受けていない場合であっても、基準日において年金給付の受給権を有する遺族がいる場合は、特別弔慰金は支給されません。 |
| 2 |
特別弔慰金の対象となる戦没者等とは、軍人、軍属または準軍属としての公務上の傷病、または勤務に関連した傷病が原因で死亡した者であること |
死因が軍人、軍属または準軍属としての公務上の傷病、または勤務に関連した傷病ではない場合は、特別弔慰金の対象となる戦没者等とはなりません。 |
支給対象となる遺族
特別弔慰金の支給対象は、援護法による弔慰金の受給権を取得した者(以下「弔慰金受給権者」といいます。)となります。また、基準日において、弔慰金受給権者が死亡等の失格事由に該当するときは、以下の「特別弔慰金支給順位表」の順番による最先順位の転給遺族となります。
| 順位 | 対象者 | 支給要件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
弔慰金受給権者(弔慰金受給権者とみなされる者を含む。) |
弔慰金の受給権者が配偶者の場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。
|
||
| 2 | 子 | 戦没者等の死亡当時の胎児を含みます。 | ||
| 3 | 父母 |
3~6順位に該当するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
|
||
| 4 | 孫 | |||
| 5 | 祖父母 | |||
| 6 | 兄弟姉妹 | |||
| 7 | 父母 |
3~6順位に必要な要件を満たしていない者 |
||
| 8 | 孫 | |||
| 9 | 祖父母 | |||
| 10 | 兄弟姉妹 | |||
| 11 |
1~10順位以外の三親等内親族(甥姪など) |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行った者
|
||
|
12 |
1~10順位以外の三親等内親族(甥姪など) |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者 |
||
基本的な持ち物
本人確認書類
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)※氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの
- 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
原則として、戸籍書類と本人確認書類(上記のうちいずれか1つ)により本人確認を行います。
※ただし、相続人、法定代理人、任意代理人(外国居住者の代理人を含む。)及び特定相続人からの請求の場合は、それぞれ手続きに必要な書類が異なります。
戸籍書類
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※その他請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。前回の特別弔慰金(第11回)を受給した方は、前回交付された裁定通知書等の資料をお持ちいただくと、手続きがスムーズに進みます。
※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。広域交付ができるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍証明書等の請求に限られます。広域交付で取得できない戸籍書類(戸籍抄本等)については、従来どおり郵送または本籍地で請求することになります。広域交付の詳細については、市民生活課ホームページをご確認ください。
請求から国債交付まで
市で請求書を受け付け、石川県及び国(厚生労働省)で審査が行われます。請求受付から国債交付までは、概ね1年程度かかる見込みです。
※請求受付開始直後は、多数の請求が集中するため、審査に、より長期間を要すると予想されますので、あらかじめご了承ください。なお、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)が石川県でない場合は、さらに時間がかかります。
注意事項
( 1 )同順位者が複数ある場合は、次の事項を承諾の上、すべての同順位者を代表して特別弔慰金の請求を行っていただくことになります。
- 権利の裁定は、すべての同順位者に対してしたものとみなされるため、他の同順位者は、権利の裁定を受けた者に対し、各々の持ち分を主張することができます。
- 他の同順位者から各々の持ち分を主張された場合は、権利の裁定を受けた者の責任で調整を行っていただきます。
- 請求書に記載した氏名及び連絡先は、特別弔慰金の請求または審査請求を行った他の同順位者に教示されます。
( 2 )確認事項が多岐にわたり、受付に時間を要するため、申請は、原則、予約制とします。事前に電話等で連絡してください。
問い合わせ
福祉総務課
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 地域福祉係 Tel:076-227-6061
Fax:076-227-6251 メール:fukushi@city.nonoichi.lg.jp