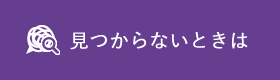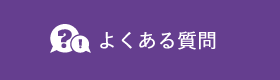国民健康保険の給付
国民健康保険の給付
医療費の手続きができるのは市役所窓口だけです。
市役所を名のり、電話やATMでの手続きを指示する詐欺に注意してください。
- 医療費の負担割合
- 70歳から74歳までの方の国民健康保険について
- 出産育児一時金
- 葬祭費
- 療養費の支給
- 高額療養費の支給(医療費が高額になったとき)
- 特定疾病(特定の病気で長期治療を要するとき)
- 入院時の食事代
- 療養病床入院時の食費・居住費
医療費の負担割合
医療機関などの窓口で、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、資格確認書または有効期限内の被保険者証を提示すれば、医療費の一部の負担で必要な治療を受けられます。ただし、年齢、所得(70歳以上75歳未満)により費用の負担割合は変わります。
| 年齢区分 | 本人の負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 2割 (現役並み所得者は3割) |
70歳から74歳までの方の国民健康保険について
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその日)から、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、資格確認書または有効期限内の被保険者証を提示することにより、自己負担割合が2割(現役並み所得者は3割)になります。
自己負担割合は、前年の所得に応じて異なります。
| 所得区分 | 負担割合 | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者 |
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人 | 3割 | |
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者1、2に該当しない人 | 2割 | |
| 低所得者 | 2 | 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人(低所得者1を除く) | |
| 1 | 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人 | ||
3割負担の人でも、下記の場合は2割負担となります。
- 70歳以上75歳未満の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満。
- 70歳以上75歳未満の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が
520万円未満。 - 70歳以上75歳未満の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度
に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満。
出産育児一時金
(1)支給額
50万円
被保険者が出産したとき、50万円(令和5年3月までの出産の場合は42万円)が支給されます。
※ただし、産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は48万8千円(令和5年3月までの出産の場合は40万8千円)となります
※妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも支給されます
(2)支払方法
直接支払制度により医療機関へ直接お支払い
被保険者等があらかじめまとまった現金を用意することなく、医療機関等において出産が行えるよう経済的負担の軽減を図ることを目的として、原則として野々市市から出産育児一時金を病院などに直接お支払いいたします。
※出産費用が50万円を超える場合、その差額分は退院時に病院などにお支払ください。また、50万円未満の場合は、その差額分を野々市市にご請求ください。
詳しくは、「国民健康保険出産育児一時金差額請求書」をご覧ください。
※出産育児一時金が野々市市から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に野々市市に申請いただく方法をご利用いただくこともできます
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いただくことになります)
(3)手続きの仕方
直接支払制度
病院などの窓口において、申請・受取に係る代理契約を締結してください。
直接支払制度を利用しない場合
保険年金課窓口にて申請してください。
申請に必要なもの、申請書の詳細は、「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」をご覧ください。
※海外で出産された方については、下記を参照してください。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人に50,000円が支給されます。
申請に必要なもの、申請書の詳細は、「国民健康保険葬祭費支給申請書」をご覧ください。
療養費の支給
急病等で治療を受けて全額を支払ったときや、コルセットなどの治療装具を作ったとき、海外で治療を受けたときは、申請により認められると、保険診療相当額が支給されます。
申請に必要なもの、申請書の詳細は、「国民健康保険療養費支給申請書」をご覧ください。
高額療養費の支給(医療費が高額になったとき)
医療機関に支払った1カ月の自己負担額(月の1日から末日までの受診について)が下記の表の限度額を超えた場合、その限度額を超えた分が高額療養費として世帯主に支給されます。入院時の食事代や保険適用外の診療は対象となりません。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
(1)70歳未満の人の自己負担限度額
| 所得区分 (基準所得額 ※1) |
3回目まで | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|
| 901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 ※2 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
同じ世帯で、過去12カ月間に高額療養費の支払いが4回以上あった場合は、上の表の「4回目以降」の自己負担限度額がを超えた分が支給されます。
※1 基準所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額です。
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
高額療養費の算定対象の考え方
高額療養費の対象となる自己負担額は、次の条件で分類したものをそれぞれ合算し、21,000円を超えたもののみが、算定対象となります。
- 月の1日から末日までの1か月(歴月)ごとの受診について計算します。
- 受診者ごと、医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも、入院と外来、医科(歯科以外)と歯科は別々に計算します。
- 院外処方で調剤を受けたときは、処方箋を出した医療機関の診療費と合算します。
- 入院時の差額ベッド代や食事療養費は対象外です。
(2)70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来 + 入院 (世帯単位) |
4回目以降 | |
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 ※3 |
3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
|
2 ※3(課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
|
1 ※3(課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
| 一般 (住民税課税所得145万円未満) |
18,000円 年間限度額 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
| 低所得者 ※4 |
2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 1 | 8,000円 | 15,000円 | ||
同じ世帯で、過去12カ月間に高額療養費の支払いが4回以上あった場合は、上の表の「4回目以降」の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
※3 現役並み所得者1・2に該当する人は、医療機関で「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなりますので交付申請をしてください。マイナンバーカードの健康保険証利用をしている場合は申請不要です。
※4 低所得者1・2に該当する人は、医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなりますので交付申請をしてください。マイナンバーカードの健康保険証利用をしている場合は申請不要です。
高額療養費の算定対象の考え方
- 外来の自己負担額は、個人ごとに自己負担額を合算します。
- 入院の場合は、世帯内の70歳以上75歳未満の人全員の入院および外来(外来の限度額を超える場合はその限度額)の自己負担額をすべて合算します。
- 75歳になる月は、上記の自己負担限度額が2分の1となります。ただし、75歳の誕生日が月の初日の場合は適用されません。
(3)高額療養費の申請
令和5年1月以後診療分の申請
自己負担限度額を超えて自己負担した場合に、自己負担限度額を超えた分が登録された口座に自動振込となります。
高額療養費申請手続き簡素化のお知らせ [PDFファイル/128KB]も参考にしてください。
口座の登録がある場合
これまでに、高額療養費の申請をしたことがあるなど、口座の登録がある場合は、登録された口座に自動振込をします。申請書の提出や領収書の提示は不要です。
口座の登録がない場合
初めて高額療養費の支給対象となったときに、高額療養費支給申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、提出をお願いします。2回目以降の支給は、自動振込となります。
注意事項
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、自動振込が停止されます。
- 公費負担医療(心身障害者医療費受給者など)による医療費補助を受けている場合は、自動振込の対象とならない場合があります。
- 口座の名義人が死亡した場合など、指定された口座に振り込むことができない場合は、改めて申請書を送付します。
- 自動振込口座の変更を希望される場合は、窓口もしくは郵送にて変更届の提出が必要です。
(4)高額療養費の世帯合算について
70歳未満の人の場合
同じ世帯で算定対象となるものが複数あった場合、それらの額を合計して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人の限度額までの自己負担額、70歳未満の人の算定対象の自己負担、それらを合計して70歳未満の人の限度額を超えた分が支給されます。
(5)「限度額適用認定証」について
入院などで医療費が高額になった場合、申請により交付される「限度額適用認定証」※を医療機関の窓口で提示することで、入院時においては自己負担限度額までに抑えられます。
ただし、国民健康保険税に未納がある場合は、交付を受けることはできません。なお、自己負担限度額は所得区分により世帯ごとに異なります(上記の(1)70歳未満の人の自己負担限度額、(2)70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を参照してください。)。
※マイナンバーカードの健康保険証利用をしている場合は不要です。なお、国民健康保険税に未納がある場合は適用されません。
申請に必要なもの
- 申請に来るする人の免許証など顔写真付きの本人確認書類
- 療養を受ける人及び世帯主の、マイナンバーカードなど個人番号のわかるもの
(6)高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯(高額療養費の算定対象世帯)に介護保険の受給者がいる場合は、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担(年間)を合算して一定の限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)を超えた場合は、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
| 所得区分(基準所得額 ※5) | 限度額 | |
|---|---|---|
| 901万円超 | ア | 212万円 |
| 600万円超 901万円以下 |
イ | 141万円 |
| 210万円超 600万円以下 |
ウ | 67万円 |
| 210万円以下 | エ | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
※5 基準所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額です。
| 住民税課税所得額 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3 | 212万円 |
| 2 | 141万円 | |
| 1 | 67万円 | |
|
一般 |
56万円 | |
| 低所得者 | 2 | 31万円 |
| 1 | 19万円 | |
特定疾病(特定の病気で長期治療を要するとき)
血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額は、1カ月10,000円までとなります(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、20,000円)。
「特定疾病療養受療証」は、申請により交付されます。
申請に必要なもの
- 免許証など顔写真付きの本人確認書類
- 世帯主と療養を受ける人の個人番号のわかるもの
- 医師の証明を受けた国民健康保険特定疾病認定申請書(申請書は保険年金課にあります)
入院時の食事代
入院時の食事負担は、1食につき510円です。ただし、住民税非課税世帯は240円(1年間の入院が90日を超えた場合は190円)となります。70歳以上75歳未満の人で、低所得1に該当する人は110円となります。
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | ||
|---|---|---|---|
| (1) | 一般((2)、(3)以外の人) | 510円(※6) | |
| (2) | 住民税非課税世帯(※7) (70歳以上の人は低所得者2) |
90日までの入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
240円 |
| 90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
190円 | ||
| (3) | 低所得者1 |
110円 |
|
(2)・(3)の人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので、医療機関に提示してください(有効期限は、7月31日ですので、引き続き必要な人は、必ず更新の申請をしてください)。マイナンバーカードの健康保険証利用をしている場合は申請不要です。
※6 指定難病患者は300円です。
申請に必要なもの
免許証など顔写真付きの本人確認書類、療養を受ける人の個人番号のわかるもの
※7 過去12か月の入院日数が90日を超えたときは、入院日数のわかるもの(領収証など)も持ってきてください。
療養病床入院時の食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を負担します。
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 右記以外の人 | 入院医療の 必要性が高い人 |
指定難病患者 | |||
| (1) | 一般((2)、(3)以外の人) | 510円(※8) | 510円(※8) | 300円 | 370円(※11) |
| (2) | 住民税非課税世帯(※9) (70歳以上の人は 低所得者2) |
240円 |
240円(※10) |
240円(※10) | |
| (3) | 低所得者1(※9) | 140円 | 110円 | 110円 | |
※8 管理栄養士などにより患者の年齢などに応じた食事が提供されていることなどの要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の保険医療機関は、470円です。
※9 減額認定証を被保険者証に添えて窓口に提出することで減額が受けられます。マイナンバーカードの健康保険証利用をしている場合は不要です。
※10 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)の場合は190円です。90日を超える入院をする場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用をしている場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
※11 指定難病患者は0円です。