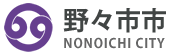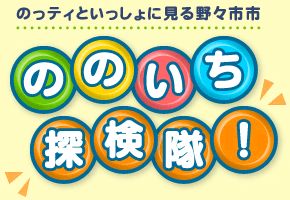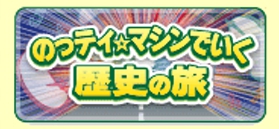本文
生活と水


この写真は新庄(しんじょう)にある南部・北部(なんぶ・ほくぶ)浄水場(じょうすいじょう)です。野々市市には浄水場が高橋町にもあり、地下水をくみ上げてそこで消毒(しょうどく)してから水を送っています。
野々市市にはじめて水道がひかれたのは、昭和42年(1967年)です。それまでは、家々で井戸をほっていました。
昭和55年(1980年)に南部・北部浄水場ができてからは、白山市(旧鶴来(つるぎ)町)にある県浄水場からの水もためることができようになりました。野々市市で使う水のおよそ5分の1が県浄水場の水です。

石川県鶴来浄水場(写真提供:石川県)
野々市市で使った水の量
(令和5年度)
- 市全体の1年間の使用量(しようりょう)
581万立方メートル
(東京ドームの約4個半分) - 市全体の1日の使用量
1万5873立方メートル
(学校のプールの約64個分) - 一人当たりの1年間の使用量
約109立方メートル
(学校のプールの約半分) - 一人当たりの1日の使用量
約297リットル
(家のふろの約1ぱいと半分)
※東京ドームの容積(ようせき)は124万立方メートル、プールは250立方メートル、家庭のふろは200から250リットルです

たくさん水を使っているね。では、使い終わったよごれた水はどうなるのかな

写真提供:石川県
この写真は、金沢市の安原川(やすはらがわ)の下流にある犀川左岸(さいがわさがん)浄化(じょうか)センターです。野々市市と金沢市・白山市の一部の地域において、便所・台所・風呂などからのよごれた水を、ここできれいな水に処理して川にもどしています。
野々市市では、昭和62年(1987年)から、道路に下水道管をうめる工事を始め、平成6年(1994年)には、建設していた浄化センターが使えるようになりました。今では、ほとんどの地域で下水道が使えるようになり、海や川などの自然を守ることにつながっています。